 
第2話(その3)
数週間後、アルフリートは王国軍司令長官ジュール・ベルトール元帥の呼び出しを受けることになった。
王国軍司令長官とは王国軍の最高首脳部に列する役職の一つで実質上クレティナス軍の最高責任者である。国王アスラール三世に何かあった場合には、ただちに王国軍最高司令官代理となって王国軍の全指揮を執る重責も担っている。この役職の者が責任を負う相手は、クレティナス王国宰相リード・ウォンテリュリーと第一五代国王アスラール三世の二人しか存在していない。
ベルトール元帥は、まだ三○代前半の貴族出身の若者ではあったが、クレティナス軍において最高の名将と名高い。高度な戦略的視眼と天才的な用兵手腕を有し、アスラール三世をして彼の偉業の最大の功労者と言わせしめたほどの男である。国王の絶対の信頼と将帥たちの絶大な信望を一身に受けて、彼はクレティナスの重鎮として存在していた。
王国軍最高司令本部ビルの最上階にあるベルトール元帥の執務室をアルフリートが訪ねたのは標準暦一○月一日のことだった。インターホンを通して参上した旨を伝えたアルフリートは、元帥の秘書官に呼ばれるのを待って部屋に入った。
「待っていたぞ、『赤の飛龍』。まあ、かけてくれ」
「失礼します」
ベルトール元帥は懐かしい表情でアルフリートを迎えた。まだ閣下と呼ばれる以前に、アルフリートは元帥が直接指揮をとる艦隊にいたことがあったのである
執務机の前に置かれた椅子に腰を降ろしてアルフリートは、偉大な英雄である元帥を仰ぎ見た。ベルトール元帥は机の向こうで立ち上がっており、アルフリートを見下ろすようにして立っていた。彼は決して偉丈夫前とした体格ではなかったが、貫禄があり堂々としたその態度は充分称賛に値するものであった。
「先に陛下からもお話があったと思うがアルフリート・クライン中将、本日付けで君を第四四艦隊の司令官職から解任し、新設される第四九艦隊の司令官に任命する」
「はい、謹んでお受けします」
「うむ、いい返事だ。……それから、これは前例のないことだが、君の艦隊は自由艦隊となることが決まっている。私と陛下から特別の命令のない限り、作戦行動はすべて君の判断に任される。それだけ、大きな責任を負うということだ。王国軍人として恥ずかしくない行動を取ってもらいたい」
「承知しております。責任の重さを痛感しますが、私の全精力をもって職務を遂行する所存です」
「よろしい、軍首脳部は君に期待している」 形式通りの動作でアルフリートに辞令を手渡して元帥は一息置いた。
「ところで、一つ君に訪ねておきたいことがあるが、答えてもらえるだろうか」
「答えられる範囲のことでしたら」
すべてと言わないところが他の軍人と違ってアルフリートらしい。
「この度の人事で君には大きな権限が与えられることになったが、その第一歩として君は何をするつもりなのか、異存がなければ聞かせてもらいたい」
「私はあまり先のことを考えるのは得意ではないのですが……」
「嘘を言うな。私は昔から君のことを知っている。考えていることを言えばいい」
元帥は苦笑して昔の部下だった青年を見つめた。彼としてはこの前例のない自由艦隊の成果に多大な期待を寄せている。もともと、案としては国王アスラール三世が考えだしたものであったが、実現までに軍部内で画策したのはベルトール元帥であり、人事面で国王にアルフリートを推薦したのもベルトール元帥であった。
「では正直に申しますと、再度ユークリッド・タイラーに挑むつもりです」
「それは個人的な意味でかね」
「いえ、戦略的な意味においてです。現在、我が国と千年帝国は交戦状態にありますが、未だ戦略的には勝利を納めていません。それは、我が国と帝国の間に三つの要塞があり、我が軍の侵入を阻んでいるからです。バルディアス、ヴァリアトゥール、エンプシャーの三門です。特に、我々が帝国へ進攻する上でもっもと最短距離にあるバルディアス方面には、現在帝国最高の名将と名高い神将タイラーがおり、鉄壁の守備を見せています」
「だったら、バルディアスを避けて通ったほうがよいのではないか」
「ええ、常識的には。しかし、それでは帝国に対する本当の意味での勝利は納めることができません。たとえ、迂回して他の門から帝国領に侵入したとしても、他の銀河の諸国はクレティナスをタイラー一人を恐れた弱小国とそしるでしょう。銀河諸国に対して有無を言わせないだけの力を示し、帝国に強い心理的ダメージを与えることができるとすれば、それは唯一、正面きっての戦いでユークリッド・タイラーを破ることだと思います」
語りながら、久しぶりに体が熱くなっていることにアルフリートは気が付いていた。不思議なものである。敵将であるタイラーの名前を出すたびに彼の体はふるえていた。
「君の見識はよくわかった。しかし、そのタイラーに勝つための具体的な作戦は考えてあるのか。戦う意志だけでは敵には勝てんぞ」
元帥は話にうなずきながらも肝心な部分が欠けているのに気付いていた。
「はい、そのことでしたらすでに案がございます。準備に時間がかかりますのでいましばらく猶予が必要ですが、元帥閣下にはいずれ近いうちにご披露したいと思っております」「では、今日はまだ見せてはくれぬというのだな」
「残念ながら」
「……わかった。君はやるといったら必ずやる男だ。信じるとしよう」
元帥は一応の満足が得られると、深くうなずいた。
「それから、必要となる物があったら何でも言ってくれ。協力は惜しまぬつもりだ」
「ありがとうございます。閣下のご期待にそえるよう微力を尽くします」
アルフリートは考えずにはいられなかった。おれは何のために帝国と戦うのだろう。国家のためなのか、国王のためなのか、あるいは銀河の平和を望む多くの人々のためなのだろうか、それとも……。タイラーとの決戦は、果たして自分の求める歴史を取り戻す戦いに必要なことなのだろうかと。
年明けには再び、彼は宇宙の人となっているだろう。新しい艦隊の準備は着々と進んでいる。とりあえず、今彼に求められる仕事は、彼の腹心になるかもしれない人事スタッフの選考であった。
アルフリートには考えることが多い。時の流れが彼に対して一歩の停滞も許してくれないようだ。
しかし、一○月一日の彼は、そんなことを忘れて元帥の執務室から退出するこにした。
忘却の歴史がある。千年の昔、数世紀以上にわたって花開いた人類最良の時代。人が人として生き、支配という名の悪魔から完全に解放されていた、あの光り輝く黄金の時代。今となっては、誰にも思い出すことができない。
人類の真実の歴史は、宇宙標準暦四九二年、惑星トランサクトに後年、千年帝国と呼ばれる銀河帝国が成立したことによって末梢された。当時、専制主義体制をとって成立した銀河帝国は、民主主義を信奉し全人類の未来を一身に担って繁栄していた銀河連邦と交戦状態にあった。もともと帝国は銀河連邦に参加する共和国の一つにすぎなかったのだが、元共和国の軍人であったグレイザー元帥のクーデターによって政権が軍事独裁体制に移行されると、ただちに連邦諸国に侵略を開始し、わずか一一年で連邦の大半を支配していたのだった。
グレイザー元帥は、連邦に広がっていた民主主義を、人間を堕落させる悪と決め付けその一掃に心血を注いだ。それに対して、連邦は必死の抵抗を試みたが、数百年に及んだ平和の時代が彼らを弱体化させ、グレイザーの率いる軍団の前に連邦の艦隊は完全な敗北を喫したのだった。そして、さらに一七年に及ぶ戦闘を経験したとき、連邦自身も民主主義の理念を忘れ、国家社会主義の名のもと戦う独裁国家へと変貌していた。
銀河の戦乱が一応の終息を見せたのは宇宙標準暦五六○年、最初の戦闘から実に七○年を経過した時のことであった。この頃には、帝国の建国者であったグレイザーはすでにこの世を去っていたが、彼の思想は大きく残り、民主主義は徹底的に末梢されることになった。もはや銀河帝国の力に逆らえるだけの勢力はなく、専制主義、貴族主義的な風潮が支配的になっていた各国では、帝国の指示にしたがって過去の歴史を抹殺したのである。そして、真実の歴史に代わって、帝国の作成した民主主義の登場しない偽りの歴史が、あたかも本物の歴史かのように後世に残されたのだった。
しかし、それから五百年後、今までの歴史に疑問を抱き人類の真実の歴史の探求に挑戦した者が登場した。偉大なる歴史研究家アウター・フォーエンである。彼は再び混迷の度合いを深めていた銀河各地におもむいて、昔の資料や失われた王朝の遺産を調べ、彼なりに真実の歴史を完成させたのだった。ところが、時代が時代であったため、不幸にも彼は当時始まったばかりの第三次銀河戦争に巻き込まれ、真実の歴史を民衆に伝えないまま、かえらぬ人になっていた。
そして、それ以降、真実の歴史は各国の王族や一部の貴族を除いて知るところでなくなり、その探究者も民主主義復活を恐れる彼らの手によって弾圧あるいは抹殺されて、何の成果もあげられないままこの世を去っていった。
その結果、人類の真実の歴史は、約千年にわたって深淵の闇のなかに眠っている。
人類の歴史を奪ったのは千年帝国であり、その初代皇帝グレイザーである。だが、千年を経過した今となっては、人類史上最大の罪を犯した彼とその仲間は存在しない。民主主義の世の中では、祖先の犯した罪の責任を子孫が負うことはないという。ならば、千年帝国を攻めることは間違いなのだろうか。……いや、彼らには罪がある。祖先が残した悪逆な遺産を継承し、それを正そうともせずに守っている。これは、人類に対するおおいな罪ではないだろうか。その意味で見れば、彼らを守護するを自らの責務とし、アルフリートの前に立ちはだかるユークリッド・タイラーは、倒すべき敵である。
そう結論付けたところで、アルフリートは思考を止めた。
「かなり、独善的だな」
第四九艦隊のために用意された王国軍ビルのオフィスのなかで、執務机について書類に目を通していたアルフリートは、自分の出した結論に気恥ずかしさを感じていた。
「しかし、人事とは面倒なものだ。いくら好きな人材を選んでいいと言っても、こんなに山ほどあるリストの中からどうやって選べって言うんだ。まったく、司令官がどうしてこんなことをやらなければならない」
机の上に山積みにされた書類を見て、アルフリートはため息をついた。彼がこんなにも苦労する理由の一つに、彼の任命した四九艦隊の首席幕僚があげられた。ファン・ラープ准将という四四艦隊時代からの彼の部下だった男なのだが、やたらに調子よく「新しい艦隊副司令官が見つかるまで私がすべての雑用を引き受けますから、閣下は人選と今後の行動計画の作成に専念していて下さい」と言ったまま、首都の繁華街へ遊びに出て行ってしまったのである。おかげでアルフリートは圧倒的な量の仕事におおわれて、すっかり勤勉の人になっていた。
「あいつ、今度帰ってきたら、絶対にただじゃあすまさないぞ」
部屋で叫んでもどうにもなるものではなかった。司令官付きの秘書官が心配して彼に濃いコーヒーを運んで来る。
「ありがとう、心配ない」
アルフリートはカップを取ると一気に飲み干した。
それにしてもと、アルフリートは考える。地位の上昇は責任の拡大を伴うのは当然だが仕事が増加するのは我慢できない。ユークリッド・タイラーは彼よりさらに高い階級にあって一方面軍の総司令官を務めているというが、いったい自分の仕事をどうやってこなしているのだろうかと。
人事や雑用をすべて中央の軍官僚に任せて自分は作戦の遂行だけに頭を使っていた、四四艦隊の司令官時代が急に懐かしく感じられるアルフリートだった。
クレティナス第四九艦隊の発足は宇宙標準暦一五六二年一二月一三日となった。最初の辞令が出てから二ヵ月以上も時間がかかったのは、アルフリートによる人選が予想以上に難航したことが大きく影響していた。
しかし、その結果として彼が選んだ人材は充分に満足がいくものだった。みな能力的には高い水準にありながら、身分や上官とのトラブルなどで不遇に甘んじていた平民出身の若い将兵達であった。艦隊副司令官兼、第一分艦隊司令官には隙のない芸術的な用兵で知られるオスカー・ベルソリック准将を、第二分艦隊司令官には知性と理論の人グエンカラー准将を、第三分艦隊司令官には強烈な攻撃を得意とする猛将スペリメンターレ・ブラゼッティ准将を任命していた。そして、艦隊司令官付き首席幕僚にはファン・ラープ准将が四四艦隊から移籍して就任した。
それから一週間後の一二月二○日、艦艇一○○○隻からなる第四九艦隊は、二五万人に及ぶ将兵と多くの人の期待を乗せて、彼らを待つ広大な星の海にその第一歩を示すことになった。
|
 |
  |
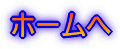
|

